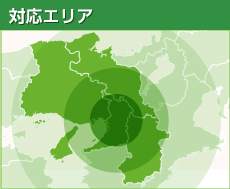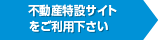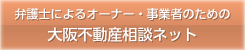持戻免除の計算と意思表示の方法
被相続人による生前の贈与や遺言により財産を取得した場合、それが特別受益とされると、計算上、その特別受益となる財産を遺産に持ち戻したうえで、法定相続分により取得すべき財産が計算されることになります(民法903条1項)。
例えば、Aの財産が1500万円存したところ、生前、子Bに500万円を贈与し、遺産1000万円を残してAが死亡し、子Bと子Cが相続人となった場合で説明しましょう。この場合、Bが贈与を受けた500万円は遺産に持ち戻されることになりますので、遺産は1500万円あるものとされます。B、Cの法定相続分は各自2分の1ですから、各自750万円を相続することになります。Bは生前に500万円をもらっていますので、相続の際には250万円だけを取得し、Cは750万円を取得することになります。
しかし、Aとしては、Bに対して、Cより多くの財産を渡したいと考えていることもあります。そこで、民法903条3項で「被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。」と規定しています。この意思表示が「持戻免除の意思表示」と呼ばれているものです。
上記の事例で、Aが持戻免除の意思表示をしていた場合、Bは500万円を遺産に持ち戻す必要がありませんので、遺産1000万円から、BとCは各自500万円を取得することになります。
持戻免除の意思表示の方法
このような持戻免除の意思表示をどのようにして行う必要があるのかですが、生前贈与の場合には、明示でも、あるいは黙示でもよいとされています。
これに対し、遺言で取得した場合には、①持戻免除の意思表示は遺言によってされなければならないとする見解(遺言必要説)と、②生前贈与の場合と同じく黙示の意思表示でもよいとする見解(遺言不要説)とに分かれています。
大阪高裁平成25年7月26日決定・判例時報2208号60頁
「特別受益は本件遺言によるものであるところ、本件遺言には持戻免除の意思表示は記載されていない上、仮に遺言による特別受益について、遺言でなくとも持戻免除の意思表示の存在を証拠により認定することができるとしても、方式の定められていない生前贈与と異なり、遺言という要式行為が用いられていることからすれば、黙示の持戻免除の意思表示の存在を認定するには、生前贈与の場合と比べて、より明確な持戻免除の意思表示の存在が認められることを要すると解するのが相当である。」
同決定は、遺言必要説に立ったのか遺言不要説に立ったのか明確にはしていませんが、結論として、持戻免除の意思表示を認めませんでした。
遺言を作成する際の注意
持戻免除の意思表示の方法につき上記のような議論がある以上、遺言で特定の相続人に財産を取得させる場合、持戻免除の意思表示も併せて行っておくべきです。
ただし、遺言で全ての財産の分割を指定する場合には持戻免除の意思表示を行う余地はありません。
また、持戻免除の意思表示を行っても、遺留分を侵害することはできないことに留意してください。