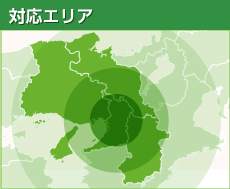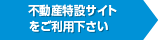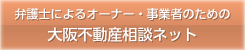危急時遺言について
危急時遺言とは?
普通の方式による遺言として、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります(民法967条)。
しかし、死が迫っているなど普通の方式による遺言を作成できない場合には簡易な要件で遺言を作成することが認められています。これが危急時遺言であり、一般危急時遺言(976条)と船舶遭難者遺言(民法979条)があります。
死亡の危急に迫った場合、公正証書遺言の作成は間に合わず、また、自筆証書遺言を作成することもできないことが多いと思われます。その場合でも、遺言者本人の意思がはっきりしておれば、危急時遺言を作成することができるのです。
平成26年に亡くなられた歌手の「やしきたかじん」さんが、お亡くなりになる4日前に病院で危急時遺言を作成されたとの報道がされましたので、危急時遺言というものがあることをご存じの方も多いかと思います。
一般危急時遺言と船舶遭難者遺言
一般危急時遺言(民法976条)
疾病その他の事由によって死亡の危急が迫った者が遺言をしようとするときは、①証人3人以上の立会いをもって、②その1人に「遺言の趣旨」を口授することによって、遺言をすることができます。この場合、③口授を受けた者がこれを筆記して遺言者および他の証人に読み聞かせるか閲覧させ、④各証人がその筆記の正確なことを承認した後にこれに署名し、押印しなければなりません。口がきけない者や耳が聞こえない者については特則があります。
そして、一般危急時遺言は、遺言の日から20日以内に、証人の1人または利害関係人から家庭裁判所に請求して確認を得なければ、その効力を生じません。
船舶遭難者遺言(民法979条)
船舶が遭難した場合において、船舶中で死亡の危急に迫った者は、証人2人以上の立会いをもって口頭で遺言をすることができます。口がきけない者が船舶遭難者遺言をする場合には、遺言者は、通訳人の通訳によりこれをすることができます。
船舶遭難者遺言は、証人が、その趣旨を筆記して、これに署名・押印し、かつ、証人の1人または利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じません。
注意点
①家庭裁判所の確認が必要
危急時遺言(一般危急時遺言、船舶遭難者遺言)は、作成後、家庭裁判所の確認が必要です(一般危急時遺言は遺言の日から20日以内、船舶遭難者遺言は遅滞なく)。これが必要とされている理由は、遺言者がみずから遺言書を作成するものではないため、証人が作成した証書の遺言の趣旨が遺言者の真意に出たものであるか家庭裁判所に審査させる必要があるからです。家庭裁判所は、遺言が遺言者の真意であると認める心証を得なければ確認することができません(民法976条5項、979条4項)。
②検認が必要
確認を受けても、別途、検認が必要です(民法1004条)。
③6ヶ月間生存したときの失効
遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から6ヶ月間生存するときは、当該遺言は効力を生じません(民法983条)。したがって、その場合、別途、遺言を作成する必要があります。
裁判例として、6ヶ月間経過したことにより失効したとした福岡高裁平成19年1月26日決定・判例タイムズ1242号281頁、本件死亡危急時遺言は前にした遺言の取消しを内容とするものであり前の遺言の効力が復活するものではないとする東京高裁平成18年6月29日決定・判例タイムズ1238号264頁があります。
後日の紛争を回避する方法
危急時遺言は本人の自筆も公証人の立会いもなく、密室で作成されますので、後日、相続人間において有効・無効をめぐって大きな争いとなることも多いようです。
もとより本人の意思は尊重すべきですが、その場合、医師の立会いや診断書の作成、録画する等、本人の真意に基づき作成されたことの証拠を残すことが、後日の争いを避けるためには必要でしょう。
裁判例
危急時遺言についてどのような争いが生じるのか、裁判例をご紹介しますので参考にしてください。
東京高裁平成9年11月27日決定・判例タイムズ984号232頁
Aは、弁護士として遺言者と従来から親交があったが、遺言者の入院当初から財産の処分についての相談を受け、数回にわたって病院に行って遺言すべき内容につき遺言者の意向を聴取していたところ、遺言者の病状が急変したとの連絡があったため、平成9年6月〇日、急遽他の証人2名を伴って病院に赴き、遺言者から従来から聴取していた内容に沿った遺言の口授を受けてこれを筆記し、これを遺言者に読み聴かせたうえ、その筆記の正確性を承認してAを含む各証人が署名押印して遺言を作成したものであることが認められるとし、本件遺言の確認をしました。
京都地方裁判所平成10年9月11日判決・判例タイムズ1008号213頁
昭和62年2月15日付け死亡危急時遺言につき、同日午後3時ころ、医師が遺言者と簡単な問答をした際、遺言者は当時が2月であること、遺言者自身が家族を集めて財産分与について話し合いたいため皆に集まってもらったと述べ、その際、医師は、遺言者には知的レベルの低下は印象として見られない、通常の応答であったとの診断をし、「病名肺癌、骨転移、上記病名のため現在の病状はきわめて危険な状態であるが、昭和62年2月15日現在、思考・判断等については異常は認められないものと思われる。」旨の診断書を作成したという事案で、当該遺言は有効としました。
東京家庭裁判所平成11年8月27日審判・家庭裁判月報52巻1号112頁
本件の遺言において法の要求する遺言者の口授があったと言えるかどうか疑問がないわけではないが、本件の遺言内容がきわめて単純であること、記載したAにおいて以前から遺言者の遺言したい内容を承知していてその作成方法の助言などもしていたこと、遺言者は病状から出血に備えて口中に脱脂綿などを含んでいたものの意識および遺言をしたいとの意欲や意思能力は備えていたこと、Aが遺言書作成の前後に記載内容を遺言者に読み聞かせたうえ遺言者が、遺言をすることも含め、その内容を理解して了解したことを手指やうなずくなどの方法で明確にしていることを総合すると、口授がない不適法な遺言として本件申立を却下するのは相当ではないとし、死亡危急時遺言の確認をしました。
最高裁第3小法廷平成11年9月14日判決・判例タイムズ1017号111頁
事案の概要
後妻Yに対し、その不動産等大部分の財産を与える旨を内容とするいわゆる危急時遺言について、先妻の子らXが、遺言当時、遺言能力がなかった旨、また、遺言者は証人が原稿を読み上げたのに対し、終始受動的であり能動的表意がないから、口授があったとはいえず、所定の要件を欠く無効な遺言であるなどと主張して、本件遺言の無効確認等を求めた事件です。
遺言者は、昭和63年9月、糖尿病、慢性腎不全、高血圧症、両眼失明、難聴等の疾病に重症の腸閉塞、尿毒症等を併発して病院に入院し、同年11月死亡した者であるが、当初の重篤な病状がいったん回復して意識が清明になっていた同年10月、Yに対し、Yに家財や預金等を与える旨の遺言書を作成するよう指示した。Yは、かねてから面識のあるA弁護士に相談のうえ、担当医師らを証人として民法976条所定の危急時遺言による遺言書の作成手続を執ることにし、また、同弁護士の助言により同弁護士の法律事務所のB弁護士を遺言執行者とすることにし、翌日、その旨遺言者の承諾を得たうえで、遺言者の担当医師であるCら3名に証人になることを依頼した。C医師らは、同月25日、A弁護士から、同弁護士がYから聴取した内容を基に作成した遺言書の草案の交付を受け、遺言者の病室を訪ね、C医師において、遺言者に対し、「遺言をなさるそうですね。」と問いかけ、遺言者の「はい。」との返答を得た後、「読み上げますから、そのとおりであるかどうか聞いて下さい。」と述べて、草案を1項目ずつゆっくり読み上げたところ、遺言者は、C医師の読み上げた内容にその都度うなずきなから「はい。」と返答し、遺言執行者となる弁護士の氏名が読み上げられた際には首をかしげる仕種をしたものの、同席していたYからその説明を受け、「うん。」と答え、C医師から、「いいですか。」と問われて「はい。」と答え、最後に、C医師から、「これで遺言書を作りますが、いいですね。」と確認され、「よくわかりました。よろしくお願いします。」と答えた。C医師らは、医師室に戻り、同医師において前記草案内容を清書して署名押印し、他の医師2名も内容を確認してそれぞれ署名押印して、遺言書を作成した。
判決
上記事実関係の下においては、遺言者は、草案を読み上げた立会証人の1人であるC医師に対し、口頭で草案内容と同趣旨の遺言をする意思を表明し、遺言の趣旨を口授したものというべきであり、本件遺言は民法976条1項所定の要件を満たすものということができるとし、遺言は有効としました。
東京高裁平成20年12月26日決定・家庭裁判月報61巻6号106頁
事案の概要
遺言者は、長年入院をしていたが、平成20年初めころに退院し、義姉の世話になりながら静養を続けていた。義姉はAから紹介を受けたD弁護士に遺言者の遺言書の作成について相談をしていたところ、同年〇月、遺言者の容態が悪化したため、Aに危急時遺言の作成を依頼し、AはD弁護士に相談し、遺言書の内容について聞いたうえで下書きを作成した。A、B、Cは、遺言者の居室に赴き、遺言者に義姉から依頼されて遺言書を作成しにきたと伝えたところ、遺言者は、その財産をすべて義姉に贈りたいと述べたので、Aは、これをメモとして書き取ったうえ、このメモを遺言者に読み聞かせ、遺言者の了解を得た。その後、Aは、本件居室から出てD弁護士に電話をし、遺言書の作成方法を聞いたうえで、本件遺言書を作成し、A、B、Cは、本件遺言書の筆記が正確なことを承認し、証人として署名した。本件遺言書には、D弁護士を遺言執行者に指定する旨の記載があるが、Aが遺言者から話を聞いたときには、遺言者はそのようなことを述べなかった。遺言者は、平成20年〇月に死亡した。
決定
裁判所は次のように述べて、遺言執行者の指定に関する部分を除き、遺言者の真意に出たものと判断しました。
「家庭裁判所は、危急時遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければこれを確認することはできないが、この確認には既判力がなく、他方でこの確認を経なければ遺言は効力を生じないことに確定するから、真意に出たものであるとの心証は、確信の程度に及ぶ必要はないものと解される。
本件では、本件遺言の証人であるA及びCは、遺言者が本件遺言の内容を話し、これを抗告人が書き取り、書き取った内容を読み上げて遺言者の確認を得た旨を述べ、Bは遺言者は話をしなかったと述べているものの、Aが遺言の内容を記載した書面を読み聞かせ、遺言者がこれに頷いたと述べている。証人らの供述には微妙な違いはあるものの、証人となった3名が遺言者との間に特別の利害を有していることを示す証拠はないから、~のとおりの事実を認定できるというべきであり、本件遺言のうち、遺言執行者の指定に関する部分を除けば、これが遺言者の真意に出たものであると認めるのが相当である。なお、上記認定のとおり、本件遺言のうち、遺言執行者の指定に関する部分は遺言者が口述していないもので、その真意に出たものとは認められない。」
東京高裁令和2年6月26日決定・判例時報2477号46頁
次のように述べて確認の申立てを却下した原審判を取り消し、危急時遺言の確認がされました。
「家庭裁判所が危急時遺言の確認をするに当たっては、当該遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得る必要があるところ(民法976条5項)、この確認には既判力がなく、他方でこの確認を得なければ当該遺言は効力を生じないことに確定してしまうことからすると、遺言者の真意につき家庭裁判所が得るべき心証の程度については、確信の程度にまで及ぶ必要はなく、当該遺言が一応遺言者の真意に適うと判断される程度のもので足りると解するのが相当である。」