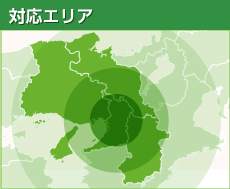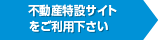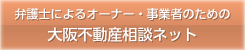相続財産の管理
被相続人が亡くなられた後、相続人の方が遺産を相続しますが、複数の相続人がいる場合、原則、遺産分割が必要です。
遺産分割が行われるまでの間、遺産共有という暫定的な共同所有関係にあり、遺産分割により、相続開始の時にさかのぼって取得することになります。
このような暫定的な遺産共有の状態における相続財産の管理をめぐって争いとなることも見受けられるところです。
相続財産の管理についてお困りの方は、当事務所にご相談いただければ、適切な助言、サポートをさせていただきます。
目次
遺産の管理費用
相続が開始してから、遺産分割が終わるまで、通常長い期間がかかります。その間、土地や不動産については、固定資産税などの管理費用がかかります。それ以外でも、火災保険料、修繕費や諸経費などが発生する場合があります。そのような遺産の管理費用について、相続人間で負担の合意ができればよいのですが、合意ができない場合に相続人間でどのように清算するかが問題になります。
「相続財産に関する費用」は、相続財産の中から支出される
「相続財産に関する費用」の償還債務は相続債務に準じるものとして、各共同相続人がその相続分に応じて負担します(民法885条本文)。そのため、「相続財産に関する費用」を支出した相続人は、他の相続人に対して費用の償還請求をすることができます。
その費用の清算について争いがある場合、管理費用は相続開始後に発生したのであり、遺産とは別個の問題であるのであるから民事訴訟で行うべきであると言えます。
しかし、管理費用の清算について相続人全員の合意があれば、これを遺産分割手続の中で清算される余地もあります。
東京高裁昭和54年3月29日決定・家庭裁判月報31巻9号21頁
分割までの遺産の管理費用については、民法第885条の規定が適用されるべきものと解するのが相当であり、また、管理費用及び分割までの間に遺産から生ずる収益については、基本となる遺産が分割されるときには、特別の事情がない限り、これに付随するものとして同時に清算することができるものと解するのが相当であって、本件においては、管理費用及び収益につきこれを遺産分割審判から除外し、他の方法(例えば訴訟)によって解決を図るのが妥当であるというような特別の事情があるとは認められないから、これを遺産の分割に当たって同時に清算する方法を採るのが相当である。
広島高裁松江支部平成3年8月28日決定・家庭裁判月報44巻7号58頁
当事者が遺産分割手続内での清算に同意している場合、または、その金額が明確で、これを遺産分割手続内で清算するのが正義、衡平にかなう特段の事情のない限り、民事訴訟によるべきものと考えるのが相当である。
占有相続人に対する建物明渡請求の可否
相続人のうち1人が遺産の不動産を占有している場合、他の相続人は占有している相続人に対し不動産の明渡しを求めることができるのでしょうか?
具体例
被相続人Aが死亡し、Xら(法定相続分2/3)とY(法定相続分1/3)が相続したところ、Yが亡Aの遺産である不動産を単独で占有しているため、XらはYに対し、多数持分権者として少数持分権者であるYに対し、多数決でもって明渡しを請求した。
最高裁昭和41年5月19日判決・民集20巻5号947頁
上記事案において最高裁は次のように述べて明渡し請求を認めませんでした。
「共同相続に基づく共有者の一人であって、その持分の価格が共有物の価格の過半数に満たない者(以下単に少数持分権者という)は、他の共有者の協議を経ないで当然に共有物(本件建物)を単独で占有する権原を有するものでないことは、原判決の説示するとおりであるが、他方、他のすべての相続人らがその共有持分を合計すると、その価格が共有物の価格の過半数をこえるからといって(以下このような共有持分権者を多数持分権者という)、共有物を現に占有する前記少数持分権者に対し、当然にその明渡を請求することができるものではない。けだし、このような場合、右の少数持分権者は自己の持分によって、共有物を使用収益する権原を有し、これに基づいて共有物を占有するものと認められるからである。従って、この場合、多数持分権者が少数持分権者に対して共有物の明渡を求めることができるためには、その明渡を求める理由を主張し立証しなければならないのである。」とし、同案件では明渡しを求める理由の主張、立証はないとしました。
「明渡を求める理由」の主張・立証
上記最判は、「明渡を求める理由を主張し立証しなければならない」としており、「明渡を求める理由」を主張・立証できれば、明渡しを求めることができると解されます。
しかし、その後の下級審裁判例を見る限り、結論としては、多数決では足らず、実際に明渡しを求めることは困難な模様です。
占有相続人に対する金銭請求の可否
最高裁昭和41年5月19日判決は、多数持分権者の少数持分権者に対する明渡し請求につき「明渡しを求める理由」が必要であるとし、原則、明渡し請求は認められていません。
それでは、相続人のうち1人が遺産の不動産を占有している場合、他の相続人は占有している相続人に対し占有利益相当額の金銭請求をすることができるのでしょうか?この点、最高裁平成8年12月17日判決が判断しています。
最高裁平成8年12月17日判決・民集50巻10号2778頁
判決内容
「共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物において被相続人と同居してきたときは、特段の事情のない限り、被相続人と右同居の相続人との間において、被相続人が死亡し相続が開始した後も、遺産分割により右建物の所有関係が最終的に確定するまでの間は、引き続き右同居の相続人にこれを無償で使用させる旨の合意があったものと推認されるのであって、被相続人が死亡した場合は、この時から少なくとも遺産分割終了までの間は、被相続人の地位を承継した他の相続人等が貸主となり、右同居の相続人を借主とする右建物の使用貸借契約関係が存続することになるものというべきである。けだし、建物が右同居の相続人の居住の場であり、同人の居住が被相続人の許諾に基づくものであったことからすると、遺産分割までは同居の相続人に建物全部の使用権原を与えて相続開始前と同一の態様における無償による使用を認めることが、被相続人及び同居の相続人の通常の意思に合致するといえるからである。」とし、同事案では、家族として同居生活をしてきたというのであるから、特段の事情のない限り、使用貸借契約が成立していたものと推認するのが相当であり、不当利得返還請求は認められないとしました。
判決の射程範囲
同最判は、①居住用の建物に、②占有相続人が被相続人の承諾を得て同居していた場合であって、③対象となる建物が遺産分割により共有関係が解消されるべき遺産共有状態にあるときには、始期付き使用貸借(相続開始を始期とし、遺産分割を終期とする使用貸借契約)の成立が推定されるものとしています。
したがって、これらの要件を満たす場合では同最判の射程範囲内となりますが、これらの要件を満たさない場合には、別途、使用貸借契約の成立の有無が判断されることになります。
特段の事情
同最判は、「特段の事情のない限り」としており、特段の事情がある場合には使用貸借契約は成立しないことになりますが、これについては個別の判断となります。
使用貸借の終了
使用貸借契約が推認される場合、相続開始時を始期とし、遺産分割終了時を終期とする使用貸借契約が成立するものとされます。ただし、いろいろな事情により、遺産分割終了前に使用貸借が終了されるとされる場合もあるでしょうし、また、遺産分割終了後に終期が到来するとされる場合もあるでしょう。
使用貸借の債務不履行解除も考えられます。例えば、占有相続人が不当に現状を変更する場合には用法違反として解除事由になる可能性があります。
金銭請求が認められる場合
占有相続人に使用貸借等の占有権限が認められない場合、占有相続人の共有持分の範囲を超えた共有物全体の占有利用は、超える部分につき法律上の原因を欠きますので、不当利得返還請求または損害賠償請求が認められることになります(最高裁平成12年4月7日判決・最高裁判所裁判集民事198号1頁)。そして、利得金額は賃料相当額とされるのが一般的です。
内縁の妻に対する請求の可否
上記最高裁平成8年12月17日判決は、相続人である妻が居住していた事案であり、妻も含めて遺産分割が行われることになります。すなわち、遺産分割の結果、妻が当該不動産を取得する可能性もあるのです。
これに対し、内縁の妻が居住している場合はどのようになるのでしょうか?内縁の妻には相続権がなく、同人が遺産分割の結果、当該不動産を取得することは有り得ません。そうすると、相続人は内縁の妻に対して不動産明渡しや賃料相当額の支払いを請求することができるのでしょうか。
最高裁平成10年2月26日判決・民集52巻1号255頁
事案の概要
- YとAとは、昭和34年ころから内縁関係にあって、楽器指導盤の製造販売業を共同で営み、本件不動産を居住及び右事業のために共同で占有使用していた。
- Aは昭和57年に死亡し、本件不動産に関する同人の権利は、同人の子であるXが相続により取得した。
- Yは、Aの死亡後、本件不動産を居住及び右事業のために単独で占有使用している。
- YとXとの間では、本件不動産の所有権の帰属をめぐる訴訟が係属し、同訴訟において、本件不動産はYとAとの共有財産(持分各1/2)であったことが認定された。
- XがYに対し、Yが本件不動産を単独で使用することによりその賃料相当額の2分の1を法律上の原因なく利得しているとして、不当利得返還を求めた。
原審判決
Yの持分を超える使用による利益につき不当利得の成立を認めて、Xの請求を一部認容した。
最高裁判決
最高裁は、次のように述べて、原判決を取り消し、高裁に差し戻しました。
「共有者は、共有物につき持分に応じた使用をすることができるにとどまり、他の共有者との協議を経ずに当然に共有物を単独で使用する権原を有するものではない。しかし、共有者間の合意により共有者の一人が共有物を単独で使用する旨を定めた場合には、右合意により単独使用を認められた共有者は、右合意が変更され、又は共有関係が解消されるまでの間は、共有物を単独で使用することができ、右使用による利益について他の共有者に対して不当利得返還義務を負わないものと解される。そして、内縁の夫婦がその共有する不動産を居住又は共同事業のために共同で使用してきたときは、特段の事情のない限り、両者の間において、その一方が死亡した後は他方が右不動産を単独で使用する旨の合意が成立していたものと推認するのが相当である。けだし、右のような両者の関係及び共有不動産の使用状況からすると、一方が死亡した場合に残された内縁の配偶者に共有不動産の全面的な使用権を与えて従前と同一の目的、態様の不動産の無償使用を継続させることが両者の通常の意思に合致するといえるからである。
これを本件について見るに、内縁関係にあったYとAとは、その共有する本件不動産を居住及び共同事業のために共同で使用してきたというのであるから、特段の事情のない限り、右両名の間において、その一方が死亡した後は他方が本件不動産を単独で使用する旨の合意が成立していたものと推認するのが相当である。」
内縁の夫婦の共有ではない場合
最高裁平成10年2月26日判決は、当該不動産が内縁の夫婦の共有であった事案でしたが、内縁の夫の単独所有であった場合、夫の相続人の内縁の妻に対する明渡し請求・不当利得返還請求は認められるのでしょうか?
大阪高裁平成22年10月21日判決、名古屋地裁平成23年2月25日判決は、内縁の夫所有の建物を内縁の妻に無償で使用させる使用貸借契約が成立していたとし、相続人の請求を認めませんでした。
大阪高裁平成22年10月21日判決・判例時報2108号72頁
内縁の夫と内縁の妻との間で、両名が同居していた内縁の夫所有の建物について、内縁の妻が死亡するまで同人に無償で使用させる旨の使用貸借契約が黙示的に成立していたとして、内縁の夫を相続した子から内縁の妻に対する建物の明渡し請求が棄却されました。
名古屋地裁平成23年2月25日判決・判例時報2118号66頁
重婚的内縁関係にある者の間において、その一方が死亡した後は他方が共同で使用してきた建物を単独で使用する旨の合意が成立していたとされました。
相続不動産から生ずる賃料の分配
相続開始後、遺産分割未了の間の不動産から生ずる賃料は誰のものなのでしょうか?
この点、最高裁平成17年9月8日判決が判断しています。
最高裁平成17年9月8日判決・民集59巻7号1931頁
判決内容
「遺産は、相続人が数人あるときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属するものであるから、この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である。遺産分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずるものであるが、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得した上記賃料債権の帰属は、後にされた遺産分割の影響を受けないものというべきである。したがって、相続開始から本件遺産分割決定が確定するまでの間に本件各不動産から生じた賃料債権は、被上告人及び上告人らがその相続分に応じて分割単独債権として取得したものであり、本件口座の残金は、これを前提として清算されるべきである。」
判決の整理
同最判により、①共同相続財産である不動産から生ずる賃料は遺産とは別個の財産であって各共同相続人がその相続分に応じて確定的に取得すること、②遺産分割は相続開始の時に遡ってその効力を生じるが各共同相続人がその相続分に応じて確定的に取得した賃料の帰属は後にされた遺産分割の影響を受けないこと、が明らかにされました。
ただし、上記最判以後も、実務上、賃料を遺産分割の対象とする旨の相続人全員の合意があれば、分割対象に含めることができるとされています。
請求できる賃料等の収益
賃料は当然に清算されるべき収益に該当します。実質的に賃料と同視されるべき共益費や返還の予定されていない礼金、権利金等も同様です。
賃貸借終了時に返還されるべき敷金は当該賃貸物件を取得する相続人に取得させることが適切かもしれません。
一方、固定資産税・都市計画税、被相続人の住宅ローン返済金、相続税などは収益から控除されるべきでしょう。
一部の相続人が相続不動産を損傷・改変した場合
相続開始後、遺産分割未了の間、一部の相続人が遺産不動産を損傷・改変した場合、他の相続人はどのような対策をとることができるのでしょうか?
この点、最高裁平成10年3月24日判決が判断しています。
最高裁平成10年3月24日判決・判例タイムズ974号92頁
妨害排除請求が可能
「共有者の一部が他の共有者の同意を得ることなく共有物を物理的に損傷しあるいはこれを改変するなど共有物に変更を加える行為をしている場合には、他の共有者は、各自の共有持分権に基づいて、右行為の全部の禁止を求めることができるだけでなく、共有を原状に復することが不能であるなどの特段の事情がある場合を除き、右行為により生じた結果を除去して共有物を原状に復させることを求めることもできると解するのが相当である。けだし、共有者は、自己の共有持分権に基づいて、共有物全部につきその持分に応じた使用収益をすることができるのであって(民法249条)、自己の共有持分権に対する侵害がある場合には、それが他の共有者によると第三者によるとを問わず、単独で共有物全部についての妨害排除請求をすることができ、既存の侵害状態を排除するために必要かつ相当な作為又は不作為を相手方に求めることができると解されるところ、共有物に変更を加える行為は、共有物の性状を物理的に変更することにより、他の共有者の共有持分権を侵害するものにほかならず、他の共有者の同意を得ない限りこれをすることが許されない(民法251条)からである。」と判示しました。
権利の濫用
ただし、「もっとも、共有物に変更を加える行為の具体的態様及びその程度と妨害排除によって相手方の受ける社会的経済的損失の重大性との対比等に照らし、あるいは、共有関係の発生原因、共有物の従前の利用状況と変更後の状況、共有物の変更に同意している共有者の数及び持分の割合、共有物の将来における分割、帰属、利用の可能性その他諸般の事情に照らして、他の共有者が共有持分権に基づく妨害排除請求をすることが権利の濫用に当たるなど、その請求が許されない場合もあることはいうまでもない。」とされています。
同事件では、畑に土砂を搬入して地ならしをする宅地造成工事を行って、これを非農地化したというのであり、共有物たる本件土地に変更を加えるものであって、他の共有者の同意を得ない限りこれをすることができず、工事差止め及び、特段の事情がない限り、土地に搬入された土砂の撤去を求めることができるとされました。