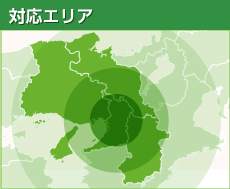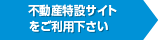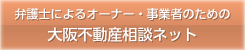相続人が取得した死亡保険金は特別受益に当たるか?
被相続人が自分を保険契約者兼被保険者、相続人Yを保険金受取人として保険契約を締結し、その後、被相続人が死亡してYが死亡保険金を受け取った場合、Yが受け取った死亡保険金はYの固有財産であり被相続人の遺産にはなりません(最高裁昭和40年2月2日判決・民事判例集19巻1号1頁)。
そこで、Yが受け取った死亡保険金は、特別受益(民法903条)に当たるか否かにつき争われてきましたが、最高裁平16年10月29日決定は、特別受益には当たらないものの、「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である。上記特段の事情の有無については、保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである。」と判断しました。
以降、上記最高裁決定の基準にしたがい、一部の相続人が受領した死亡保険金について民法903条の類推適用により特別受益として持ち戻しの対象となるか否か争われてきましたが、類推適用を肯定した東京高裁平成17年10月27日決定、名古屋高裁平成18年3月27日決定、否定した大阪家裁堺支部平成18年3月22日審判など公表された裁判例は少ししかありませんでした。
そうしたところ、類推適用を否定する広島高裁令和4年2月25日決定が現れましたので、これまでの裁判例とともにご紹介します。
最決平16・10・29民集58巻7号1979頁
Xら及びYは、いずれもAとBの間の子であり、Aは平成2年1月に、Bは同年10月に、それぞれ死亡しました。
遺産
⑴ 土地 1149万円
⑵ その余の遺産
①Xら3名取得分 計3862万8904円
②Y取得分 1387万8727円
⑴、⑵計6399万7631円
Yが取得した養老保険契約及び養老生命共済契約に係る死亡保険金等
ア 養老保険の死亡保険金500万2465円
イ 養老保険の死亡保険金73万7824円
ア、イ計574万0289円
上記死亡保険金等が民法903条1項の特別受益に該当するか否か
「被相続人が自己を保険契約者及び被保険者とし、共同相続人の1人又は一部の者を保険金受取人と指定して締結した養老保険契約に基づく死亡保険金請求権は、その保険金受取人が自らの固有の権利として取得するのであって、保険契約者又は被保険者から承継取得するものではなく、これらの者の相続財産に属するものではないというべきである(最高裁昭和36年(オ)第1028号同40年2月2日第三小法廷判決・民集19巻1号1頁参照)。また、死亡保険金請求権は、被保険者が死亡した時に初めて発生するものであり、保険契約者の払い込んだ保険料と等価関係に立つものではなく、被保険者の稼働能力に代わる給付でもないのであるから、実質的に保険契約者又は被保険者の財産に属していたものとみることはできない(最高裁平成11年(受)第1136号同14年11月5日第一小法廷判決・民集56巻8号2069頁参照)。したがって、上記の養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権又はこれを行使して取得した死亡保険金は、民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらないと解するのが相当である。もっとも、上記死亡保険金請求権の取得のための費用である保険料は、被相続人が生前保険者に支払ったものであり、保険契約者である被相続人の死亡により保険金受取人である相続人に死亡保険金請求権が発生することなどにかんがみると、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である。上記特段の事情の有無については、保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである。
これを本件についてみるに、~ア及びイの死亡保険金については、その保険金の額、本件で遺産分割の対象となった本件各土地の評価額、前記の経緯からうかがわれるBの遺産の総額、Xら及びYと被相続人らとの関係並びに本件に現れたXら及びYの生活実態等に照らすと、上記特段の事情があるとまではいえない。したがって、~ア及びイの死亡保険金は、特別受益に準じて持戻しの対象とすべきものということはできない。」
民法903条の類推適用を認めた裁判例
東京高決平成17・10・27家庭裁判月報58巻5号94頁
「抗告人が〇〇生命保険⑴⑵により受領した保険金額は合計1億0129万円(1万円未満切捨)に及び、遺産の総額(相続開始時評価額1億0134万円)に匹敵する巨額の利益を得ており、受取人の変更がなされた時期やその当時抗告人が被相続人と同居しておらず、被相続人夫婦の扶養や療養介護を託するといった明確な意図のもとに上記変更がなされたと認めることも困難であることからすると、一件記録から認められる、それぞれが上記生命保険金とは別に各保険金額1000万円の生命保険契約につき死亡保険金を受取人として受領したことやそれぞれの生活実態及び被相続人との関係の推移を総合考慮しても、上記特段の事情が存することが明らかというべきである。したがって、〇〇生命保険⑴⑵について抗告人が受け取った死亡保険金額の合計1億0129万円(1万円未満切捨)は抗告人の特別受益に準じて持戻しの対象となると解される。
また、抗告人は、平成8年5月〇日、保険料が全納されていた〇〇生命保険⑶の契約者、受取人となることにより、被相続人から契約上の地位の移転を受けたものであり、これが生計の資本としての贈与にあたるものであり、その相続開始時の解約返戻金額441万円をもって特別受益額と評価するのが相当である。」
名古屋高決平成18・3・27家庭裁判月報58巻10号66頁
原審・岐阜家裁平成17年4月7日審判・家庭裁判月報58巻10号74頁の判断を一部修正のうえ支持しました。
「死亡保険金等の合計額は5154万0864円とかなり高額であること、この額は本件遺産の相続開始時の価額の約61%(*高裁修正後)、遺産分割時の価額の約77%を占めること、被相続人と申立人との婚姻期間は3年5か月程度であることなどを総合的に考慮すると上記の特段の事情が存するものというべきであり、上記死亡保険金等は民法903条の類推適用により持戻しの対象となると解するのが相当である。」
民法903条の類推適用を否定した裁判例
大阪家堺支決平成18・3・22家庭裁判月報58巻10号84頁
「申立人は、『相手方Bの受領した上記死亡保険金428万9134円は、相手方Bの特別受益に当たる。』旨主張する。しかしながら、簡易保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権又はこれを行使して取得した死亡保険金は、民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産に当たらないと解するのが相当であるし、相手方Bが受領した死亡保険金は合計428万9134円であるところ、これは被相続人の相続財産の額6963万8389円の6%余りにすぎないことや、~のとおり、相手方Bは、長年被相続人と生活を共にし、入通院時の世話をしていたことなどの事情にかんがみると、保険金受取人である相手方Bと他の相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らして到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存在するとは認め難いから、同条の類推適用によって、相手方Bの受領した上記死亡保険金428万9134円を、特別受益に準じて持ち戻しの対象とすべきであるとはいえない(最高裁平成16年10月29日決定・民集58巻7号1979頁参照)。」
広島高裁令和4年2月25決定判時2536号59頁・判タ1504号115頁
「本件死亡保険金の合計額は2100万円であり、被相続人の相続開始時の遺産の評価額(772万3699円)の約2.7倍、本件遺産分割の対象財産(遺産目録記載の財産)の評価額(459万0665円)の約4.6倍に達しており、その遺産総額に対する割合は非常に大きいといわざるを得ない。しかしながら、まず、本件死亡保険金の額は、一般的な夫婦における夫を被保険者とする生命保険金の額と比較して、さほど高額なものとはいえない。次に、前記の本件死亡保険金の額のほか、被相続人と相手方は、婚姻期間約20年、婚姻前を含めた同居期間約30年の夫婦であり、その間、相手方は一貫して専業主婦で、子がなく、被相続人の収入以外に収入を得る手段を得ていなかったことや、本件死亡保険金の大部分を占める本件保険1について、相手方との婚姻を機に死亡保険金の受取人が相手方に変更されるとともに死亡保険金の金額を減額変更し、被相続人の手取り月額20万円ないし40万円の給与収入から保険料として過大でない額(本件保険1及び本件保険2の合計で約1万4000円)を毎月払い込んでいったことからすると、本件死亡保険金は、被相続人の死後、妻である相手方の生活を保障する趣旨のものであったと認められるところ、相手方は現在54歳の借家住まいであり、本件死亡保険金により生活を保障すべき期間が相当長期間にわたることが見込まれる。これに対し、抗告人は、被相続人と長年別居し、生計を別にする母親であり、被相続人の父(抗告人の夫)の遺産であった不動産に長女及び二女と共に暮らしていることなどの事情を併せ考慮すると、本件において、前記特段の事情が存するとは認められない。」
(弁護士 井上元)