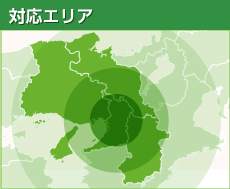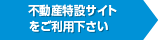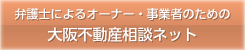使途不明金に関する東京地判令和3・9・28
相続開始後、一部の相続人Yが被相続人Aの生前にA名義の預金口座から多額の出金をしていたことが判明することがあります。
この場合、XはYに対して、不法行為に基づく損害賠償請求や不当利得を原因とする不当利得返還請求を行うことになります。
このXのYに対する請求につき、東京地判令和3・9・28判時2528号72頁が、①YがAの生前にAの預金口座等からAに無断で出金し、これに対しXが、Aから相続した不当利得返還請求権を行使する場合の権利割合は法定相続分である、②YがAの死後、遺産であるAの預金口座からXに無断で出金し、Xが、不当利得返還請求権を行使する場合の権利割合は法定相続分である、と判断しています。
使途不明金の返還請求訴訟については、①名古屋地方裁判所民事プラクティス検討委員会「被相続人の生前に引き出された預貯金等をめぐる訴訟について」判タ1414号74頁、②長田雅之「被相続人の生前に払い戻された預貯金を対象とする訴訟についての一試論‐最近の第一審裁判例の分析」判タ1500号39頁が公表されています。その後の裁判例として、東京高判令和4・4・28金融・商事判例1650号16頁(Aの存命中にA名義の預金口座から預金を払い戻したYには払戻権限があったため、XからYに対する不法行為の損害賠償請求権または不当利得返還請求権は認められないが、YとAの間には、払い戻した預金に関し、寄託契約が成立していたとして、XからYに対する寄託金返還請求と認めています)があります。
東京地判令和3・9・28判時2528号72頁
1 Xが本件生前出金に係るAのYに対する請求権について分割承継した金額はいくらか
⑴ Yが、Aの許諾を得ることなく、本件生前出金を得たものと認められること(略)からすれば、Aは、生前、Yに対し、同額の不当利得返還請求権を有していたものといえる。
Xは、別件判決に基づき、本件生前出金のうち、法定相続分である2分の1に相当する4716万7657円については、YないしCから支払を受けており(略)、本件請求は、Xの法定相続分2分の1とX主張の具体的相続分との差額の支払を求めるものであるから、本件生前出金に係る上記不当利得返還請求権が、法定相続分ではなく、X主張の具体的相続分の割合で、Xに相続されたといえるかどうかが問題となる。
⑵ そこで、検討するが、相続人が数人ある場合において、その相続財産中に金銭その他の可分債権があるときは、その債権は法律上当然分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継するものと解され(昭和29年小法廷判決)、上記⑴の不当利得返還請求権もまた、法律上当然分割され、XとYの相続分に応じて権利が承継されるものと解される。
Xは、ここでいう相続分が法定相続分ではなく、具体的相続分であると主張するのでこの点について検討する。
ア まず、具体的相続分とは、相続開始時にAが有していた財産の額を相続開始時の評価額で数量化し、これに相続人が受けた特別受益の額を加算し、寄与分の額を控除して算出したみなし相続財産に、相続人の法定相続分又は指定相続分を乗じて算出した一応の相続分を基礎とし、特別受益を受けた者についてはその特別受益の額を控除し、寄与分のある者については、寄与分の額を加えて、それぞれ算出した相続分である(民法903条、904条の2)。
このように、具体的相続分とは、遺産分割手続における分配の前提となるべき計算上の価額又はその価額の遺産の総額に対する割合を意味するものであって、それ自体が実体法上の権利関係に当たるものではない(最高裁判所平成12年2月24日第一小法廷判決・民集54巻2号523頁参照)。
イ 具体的相続分を算出するには、特別受益や寄与分の算出が必要となるところ、特に、寄与分に関しては、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して家庭裁判所において定められるべきもので、これを離れて家庭裁判所の手続外でこれを定めることはほとんど不可能である。
また、特別受益についても、特別受益となりえる贈与の有無やその額は事実上、相続開始時点では不明であるというほかない。
さらにいえば、特別受益、寄与分のいずれについても、遺産分割の場面において、相続人間の公平を図るために考慮されるものであり、遺産分割手続の際に、それらの申立て又は主張がない場合には考慮されないのであるから、これらの考慮の結果としての具体的相続分を相続開始時に何らかの方法で特定、算出することは困難である。
以上によれば、相続開始の時点で具体的相続分を具体的に、かつ正確に把握することはほとんど不可能に近いというほかない。
これに対し、法定相続分又は指定相続分は、相続開始時点でも相当程度明確に定まっているといえる。
ウ 以上を踏まえると、昭和29年小法廷判決が、可分債権は、その相続分に応じて、相続開始と同時に当然に分割されるとしつつ、その相続分については、相続開始時点では定まっていないか、少なくともこれを具体的に把握することがほとんど不可能に近く、また、遺産分割手続における分配の前提となるべき計算上の価額又はその価額の遺産の総額に対する割合にすぎず、実体法上の権利関係とはいえない具体的相続分を指しているとは解し難い。
Xの主張するような解釈を採ると、相続開始と同時に分割されたはずの金銭債権の相続割合は、結局のところ、遺産分割時点まで明確に定まらないこととなり、Aの有していた可分債権に当たる金銭債権の行使は、遺産分割が終了するまでの間、事実上困難なものとなりかねないし、当然に分割されたことで遺産分割の対象とはならないはずの可分債権が、実質的には遺産分割の対象とされる結果になりかねず(当然分割された可分債権は原則として遺産分割の対象とはならず、共同相続人間の合意がある場合に限り遺産分割の対象として取り扱われるとするのが、当時の遺産分割手続における実務の一般的運用である)、このような事態は、昭和29年小法廷判決が、可分債権を当然に分割されるものとしたことと整合しない結果になることは明らかである。
エ Xは、Yが違法な本件生前出金をしなければ、本件生前出金に係る出金相当額も含め、XとYの間で公平に分割されていたはずであり、同出金相当額に係る本件不当利得返還請求権が法定相続分の2分の1で分割されてしまうと、違法な行為をした方が、違法な行為をしなかった場合と比較して不当に利益を得る結果となるなどとして、その結論の不当性を強調する。
しかし、可分債権については、相続開始時に当然に分割されるとする昭和29年小法廷判決を前提とする限り、可分債権については、その相続開始時に明確に定まっている法定相続分又は指定相続分により、当然に分割されると解するほかはなく、Xにおいて、上記で指摘した昭和29年小法廷判決をはじめとする判例理論に伴う理論的な問題点や実際上の不都合を克服するに足りる十分な説明がなされているとはいえない。
また、Xが本件の結論と比較する、遺産分割時点における共同相続人間の公平性についても、それは、あくまでも、相続開始時に存在するAの財産のうち、未分割のもので、かつ、遺産分割時に現存する範囲の財産について相続分に応じた分割が行われるのが原則であって、Aに帰属したあらゆる財産が相続分に応じて分割されるものではないし、特別受益者については、その具体的相続分を超える特別受益を受けていても、単にその相続分がなくなるというにとどまり、超過した特別受益の返還までは求められないなど、公平な分割といっても、そこには一定の限界があるものである。
本件についても、Xは、本件生前出金がなければ、遺産分割時点でこれら出金額に相当する財産についても遺産となり、Xが相続できた範囲がより広がっていたことを当然の前提としているが、そもそも本件生前出金がなかったとしても、相続開始時点及び遺産分割時点で、本件生前出金に係る金員相当額が現存していたかどうかは明らかでないし、Xは、本件生前出金に係る金銭の2分の1に相当する額である4716万7657円については、既に支払を受け、遺産分割においても、別件調停に代わる審判により、実質的にはすべての遺産を取得したと評価できるような分割を受けているのであるから(略)、XとY間の公平性が著しく損なわれているとまではいえない。
オ 以上によれば、本件生前出金に係る不当利得返還請求権は、相続開始と同時に、法定相続分により、当然に分割されたものであり、この法定相続分に相当する金銭については、既にYからXに支払がなされているから、本件生前出金について、既払額を超える額の支払を求めるXの請求には理由がない。
2 本件死後出金は、Xの損失の下、Yが法律上の原因なく利得したものか
⑴ 本件死後出金の全額につき法律上の原因がない利得といえるか
ア 本件死後出金がなされた本件口座は、預金口座であるから、本件死後出金前は、本件死後出金に係る出金相当額を含め、遺産を構成するものであったと解される(最高裁平成28年大法廷決定)。なお、Yは、本件死後出金は、最高裁平成28年大法廷決定よりも前になされたとして、同決定は遡及適用されないなどと主張するが、同決定は、預金債権は、可分債権に当たらない旨の解釈を示したものである以上、同決定前に出金がなされた預金口座に係る預金債権にも同様の解釈が及ぶことが否定される理由はない。
イ もっとも、上記1⑵アで説示したとおり、具体的相続分とは、遺産分割手続における分配の前提となるべき計算上の価額又はその価額の遺産の総額に対する割合を意味するものであって、それ自体が実体法上の権利関係に当たるものではない。したがって、本件死後出金がなされた時点で、Xが本件口座に関し、具体的相続分に相当する実体法上の権利を有していたとはいえないし、Yに法定相続分に相当する実体法上の権利がなかったともいえない。そうすると、Yによる、本件死後出金は、Yの法定相続分の範囲にとどまる限り、法律上の原因のない利得ということはできないし、Xにそれに対応した損失があるともいえず、本件死後出金の全額について、Yの不当利得が成立するとはいえない。本件死後出金の額合計259万6432円の2分の1に相当する額129万8216円を超えた部分の限度で不当利得の成否が問題となるにすぎないというべきである。
なお、この点につき、Yは、本件死後出金の額259万6432円のうち、本件口座の相続開始後の残高に相続開始後の入出金を考慮した最終残高259万7161円(略)の2分の1に相当する129万8580円の差額129万7852円の限度で不当利得の成否が問題となるにすぎないと主張する。
しかし、本件死後出金に係る本件口座は、最高裁平成28年大法廷決定のとおり、本件死後出金時点で、Aの遺産であったのであるから、結局、本件口座は、XとYにおいて、各2分の1の潜在的な持分割合による準共有状態にあったものと解されるのであり、本件口座の預金残高を数量的に2分の1に分けた金額それぞれをXとYが有しているというものではない(XとYは、預金残高の全体について2分の1の割合の準共有持分権を有しているものである)。したがって、本件口座の最終残高に関わらず、本件死後出金の額である259万6432円の全額について、XとYの準共有状態にあった財産の逸出となるから、その2分の1に相当する金額については、Xに対する準共有持分権の侵害となり、不当利得を構成し得るものである。
ウ Yは、Xが遺産分割調停の際には、本件死後出金に係る金員は既分割として遺産に含めないことに合意しており、その不当利得返還請求は自己矛盾ないし禁反言則に反する、遺産分割においてYが具体的相続分を超過する財産を受領していたとしても、その返還を求めることはできない(民法903条2項)などとも主張する。
しかし、遺産分割調停当時のXの主張書面を見ても、本件死後出金が既分割であるなどとは主張しておらず、かえって不当利得による返還を求める意思を示しているし(略)、既に出金がなされた以上、当該出金に係る部分は、遺産分割時に現存しない財産として、遺産に当たらないのであるから、Xが、本件死後出金を遺産分割調停時点で、遺産に掲げていなかったとしても、そのことから、本件死後出金に係る不当利得返還請求権を行使することが自己矛盾であるとか、禁反言則に反するなどとはいえない。
また、Xの不当利得返還請求権は、Yによる本件死後出金が、Xの相続権を侵害するものとして、その返還を求めるものであって、特別受益の返還を求めるものではないから、超過特別受益の返還が求められないこと(民法903条2項)は、同不当利得返還請求権行使の可否に影響するものではない
⑵ 本件死後出金につき、必要な費用に充てたものとして不当利得とならないか
ア 医療費13万7900円(略)については、別件判決において、Aの生前の出金額から必要な費用として控除されているから(略)、本件死後出金に係る金員をもって、上記医療費に充てたものとは認められない。
イ 葬儀費用等、墓所移動費用の合計226万6501円(略)については、いずれも当然に共同相続人が相続分に応じて負担すべき性質の費用とはいえないところ、Aの生前に、その死後に要することとなったこれら費用について、明確にYにその出捐をゆだねていたと認めるに足りる証拠はなく、当該費用支出の時点で、Xの承諾を得たとも認められない。そうすると、これら費用はXが負担すべきものとはいえず、当該費用出捐の原因となる葬儀等を主宰したと考えられるYにおいて負担すべき費用である。したがって、仮に、本件死後出金をこれら費用に充てていたとしても、それはYが負担すべき費用に充てたというにすぎず、その限度でYは、Xの損失の下、利得を得たといえるし、その利得に法律上の原因があるとはいえない。
ウ よって、本件死後出金について、必要な費用に充てたものとして不当利得の成立が否定される部分はないから、Xは、Yに対し、本件死後出金のうち、Yの法定相続分を超過した129万8216円の限度で、不当利得返還請求権を有する。
⑶ 本件死後出金に関し、Yは悪意の受益者か
本件死後出金は、相続開始後になされたものであり、遅くとも最終の出金時点である平成26年11月2日の時点までは、Yの法定相続分を超える限度で出金がなされたものである(略)。これによれば、Yは、遅くとも同日時点までに法律上の原因がないことを認識していたというべきであるから、Yは本件死後出金に係る不当利得129万8216円について、同日の翌日である同月3日以降の法定利息を返還すべきである。
(弁護士 井上元)